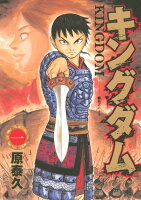はじめに
孫子の兵法とは、世界で最も古いと言われている「戦い方をまとめたもの」です。
なぜ、「孫子の兵法」がいいのか?
それは
・ビジネスシーンに通ずる応用性や可能性に溢れているから
・内容が不変的だから です。
孫子とは?
孫武が書いた本が孫子(孫子の兵法)です。 孫子とは「戦に勝つため、負けないための方法をまとめた書物」です。
要点
・敵を知り、自分を知る
・主導権を握る
・意表を突く
・正攻法と不意打ち
・敵に合わせた戦い方
・勝算がなければ戦わない
・守りは慎重に、攻めはスピード重視
・柔軟に 合理的に 無理をしない
トピック
計画力(始計篇)
5つのテーマと7つのチェックリストで戦いの見通しをつける
5つのテーマ
道・・・トップと兵の目的意識が統一されていること(一体感を持っていること)
天・・・戦う前の天候、季節、時間の条件を知る
地・・・地理(地形)的な条件を知る(距離、険しさ、広さ、高さなど)
将・・・リーダーが有能かを確かめる
法・・・組織の編成、秩序を確かめる
7つのチェックリスト
1.トップはどちらが立派な政治を行っているか?
2.役職者はどちらが有能か?
3.天と地のテーマはどちらが有利か?
4.規律はどちらが徹底しているか?
5.全体の士気(エネルギッシュさ)はどちらがあるか?
6.兵はどちらが訓練されているか?
7.賞罰の公平さはどちらにあるか?
この7つのチェックリストを満たさなければ、敵との争いは避けるべきである
孫子いわく、「勝利への見通しが立つのは条件が揃っているからである」
スピード力(作戦篇)
争いにはお金がかかることを念頭に置く
会社と同じように事業が活発になれば大きな資金が必要になってくる。
そこで孫子は短期決戦のススメを説いている。
長期戦になるとどのようなデメリットがあるか?
・兵の士気(モチベーション)が落ちる
・資金が底をつく
結果的に長期戦になると損失が大きくなっていくため、戦う時はスピード感を持つこと
知力(某攻篇)
最高の勝ち方は戦わずして勝つ
つまり、武力ではなく政治的戦略を行使すること。
武力行使は犠牲も損失も大きくなるため、城攻めは最終手段だと説いている。
優れた戦い方とは?
・敵の意図を見抜いて先手を打つ
・敵を孤立させる
・劣勢ならば潔く撤退する
・反撃への準備をする
・勝算がなければ戦わない
・敵の実力を把握し、自分の実力も把握する(=彼を知り己を知れば百戦殆からず) そして、戦上手は無理なく自然に勝つので、その勇敢さや知略は人目につかない
適応力(軍形篇)
戦い方の形(型)を固定しないことが重要
孫子は理想の形を水に例えている。
兵の形は水のような順応性が重要。
そして、攻守の選択を誤らないこと。
事前の準備力と総合的な判断をするには?
・国土の広さ
・資源の多さ
・人口の多さ
・兵力の強さ
・勝敗のゴールは?
この5つの要素をふまえて安全な勝ち方を考える。
勝機がなければ守りに徹し、勝機があればすかさず攻めに転じる。
そのときに敵に守るスキを与えず攻め立てることが重要である
集団力(兵勢篇)
全員の力を一つにまとめて勢いに乗る
まずは指揮系統の確立。
個人の能力をまとめた集団の力を引き出すことで勢いがつく。
勢いに乗ることで勝利につながる。
・集団力を左右するのは統制力による
・士気を左右するのは勢力による
・強弱を左右するのは兵の態勢による
勝利するためには集団の力が重要である
マイペース力(虚実篇)
自分が主導権を握るように行動する
まずはじめに、余裕を持って作戦を練ることが重要である。
主導権を握るためには?
・疲れさせないために敵のいないところを狙う
・攻め勝つために敵が守り固めていないところを狙う
・敵の攻めにくいところで守り抜く
・敵がどこを守れば良いかわからないような攻め方をする
・敵がどこを攻めれば良いかわからないような守り方をする
攻めるときは相手の不意を突き、退却するときは素早く撤退する。
勝つためには、相手のペースに飲まれずに、自分のペースをしっかりと保つこと
注意力(軍争篇)
トレードオフの本質を知る
勝ちを狙うとリスクが伴うことを理解すること。
例えば・・・ ・重装備で戦地へ向かえば、敵の動きに遅れをとる
・軽装備で戦地へ向かえば、物資を欠き不利になる
・必死になりすぎると命を落とす
・助けを乞うと捕まる
・気が短いと敵の術中にハマる
・素直さだけでは敵の挑発に乗せられる
・思いやりすぎると神経をすり減らす
「急がば回れ」と「禍を転じて福となす」をモットーに、敵の裏をかくことが重要である。
何かを得ようとすると同時に何かを失う。
このことを念頭に合理的な勝ち方を選ぶこと
バランス力(九変篇)
一つのことにとらわれない臨機応変さ
視野が狭くなると余裕を失う。
つまり、冷静さを失うので負けにつながる。
臨機応変の9つの原則
1.高い場所にいる敵は攻めるな
2.丘を背にした敵とは正面から攻めるな
3.おとり退却の敵を追うな
4.おとりの敵を相手にするな
5.強い相手とは戦うな
6.戦いを降りている敵とは戦うな
7.敵を包囲したら逃げ道をあけておく
8.追い詰めた敵を深追いしない
9.離れた敵地に長くとどまらない
現代に置きかえるならば、経済情勢の変化に期待せず、どんな経済情勢でも対応できる心構えを備えておくことが重要である。
大切なことは心構えである。
観察力(行軍篇)
敵の動きを察知することで本質を見抜く
目の前で起きていることに疑問を抱くことで物事の本質が見えてくる
例えば、土ぼこりの舞い上がり方で敵の動勢を察知する方法
・土ぼこりが高く舞えば戦車が攻めてきている。
・土ぼこりが一面に舞い上がれば歩兵部隊が攻めてきている。
・土ぼこりがあちらこちらでスジのように舞がれば敵兵が休憩をしている。
・土ぼこりがわずかに移動しながら舞い上がるのは敵が宿泊準備をしている。
観察眼を鍛えることで敵の動勢をいち早くキャッチし勝利へ結び付ける
俯瞰力(地形篇)
戦いを有利に運ぶためにはその地の利を知ること
6つの地形と6つの負けパターン
6つの地形の種類
通(つう)・・・道が四方に通じている場所
桂(かい)・・・進攻には良いが撤退しにくい場所
支(し)・・・敵にも味方にも不利な場所
隘(あい)・・・狭い場所
険(けん)・・・険しい場所
遠(えん)・・・遠く離れた場所
6つの負けパターン
走(そう)・・・1(味方):9(敵)の状態で戦うとき
弛(し)・・・兵たちは強いが上官が弱いとき
陥(かん)・・・上官は強いが兵たちが弱いとき
崩(ほう)・・・幹部内での折り合いが悪く、命令に従わず自分勝手に戦うとき
乱(らん)・・・統制が取れずに戦闘配置、采配がでたらめなとき
北(ほく)・・・情報不足で味方に精鋭部隊がいない状態で強い敵と戦うとき
敵、味方、地形を正しく把握することが勝負の分かれ目である。
地形を知ることは勝負を有利に進めるが、それとは別に指導者の責務も問われる
分類力(九地篇)
状況を9つにカテゴライズする
戦場の地形に応じた戦い方がある
9つのケース
散地・・・自分の領土が戦場のとき。この場合、戦いを避けるべきである。
軽地・・・敵の領土に少し踏み込んだ戦場のとき。この場合、その地域にとどまってはならない。
争地・・・争点(占領すれば有利になる領土)戦場のとき。占領されたら攻撃してはならない。
交地・・・自分も敵も進攻可能な戦場のとき。この場合、部隊の結束力を固くする。
衢地・・・多くの勢力に隣接した戦場のとき。この地では外交交渉をするべきである。
重地・・・敵の領土に深く入り込んだ戦場のとき。現地調達を心がけるべきである。
圮地・・・進軍が困難な戦場のとき。この場合、速やかに通過すべきである。
囲地・・・入りやすく逃げにくい戦場のとき。奇策を用意するべきである。
死地・・・死ぬ気で戦わないと全滅する戦場のとき。この場合、戦うしかない。
状況を知らずに戦うと負ける。
死を覚悟したとき人間は強さを発揮する。
現代においては人に死を覚悟させることは許されない。
そのような状況をいかに作り出せるかが腕の見せどころである。
感情コントロール力(火攻篇)
目的を遂げるために感情的であってはならない
慎重の上に慎重を重ね、客観的な判断を下す ・戦いには目的がある。
勝っても目的を遂げなければ結果として失敗である。
・目的を見失わないことである。
・やむを得ない場合以外は戦いを起こさない。
・怒りや感情にまかせて戦いを起こさない。
・戦いの結果を考慮し、客観的判断に基づいた行動をする。
・ それでも火攻めを行うときには
・空気が乾き切った頃を選択
・星座を見て判断する
火攻めに際して天候を選ぶのは風が吹き起こる頃を狙うからである。
火攻めには様々な判断材料が必要である。
指導者は石橋を叩いて叩いて慎重に物事にのぞむこと
情報収集力(用間篇)
情報活動に費用を惜しんではならない
スパイを使って「敵を知る」
5種のスパイ
郷間・・・敵の住民を使って情報収集
内間・・・敵の役人を買収して情報収集
反間・・・敵のスパイを自分のスパイにする
死間・・・死を覚悟して敵地に潜入する
生間・・・敵地から生還し情報を共有する
スパイをうまく活用し、生きた情報を集める。
勝つ人間は情報収集で先んじている。
先に知る者が勝つ
さらに詳しくわかりやすく知りたい方は
孫子の兵法をもっとわかりやすく詳しく学びたい人に向けてオススメを紹介します。 気になった本があればアマゾンレビューを参考してみてはいかがでしょうか。
以上、孫子の兵法をビジネスシーンに活用してみてはいかがでしょうか?
![]()
![]()